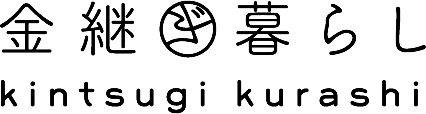金継ぎについて調べてみると、『新うるし』とか『簡易金継ぎ』といった言葉を目にすると思います。
「かぶれづらい」とか、「簡単にできる」といったメリットが書かれているものの、中には「安全じゃない」「食器に使えない」といったデメリットも書かれていて疑問や不安になる方も多いと思います。
そんな方にもわかりやすいように、新うるしを使った簡易金継ぎのことについて説明していきます。
新うるしは商品名のこと
新うるしというのは、櫻井釣漁具株式会社から販売されている『ふぐ印 新うるし』のことです。
[itemlink post_id=”3573″]
商標登録はされていないようなので、もしかしたら他のメーカーからも同じ名前で出ているかもしれません。
簡単に言ってしまうと、新うるしというのは商品名のこととも言えます。
新うるしは、うるしに似た塗料
では、新うるしは何で出来ているのかというと、漆の木ではなく、カシューナッツの殻から抽出した物が多いです。
新うるしを作っているメーカーごとで成分や原料などは違うと思いますが、ほとんどがうるしに似せた塗料、合成うるしになります。
一般的に用いられている「合成うるし」には二様の意義がある。
すなわちその1は漆器に使用することのできる代用うるしの意味と、その2は天然うるしの主成分またはそれに類似する組成をもつ塗料という意味の二つである。
(中略)
天然うるしの資源のふっていから漆器に使用することのできる代用うるし塗料の出現は、この業界における久しい待望であった。
(中略)
天然うるしにきわめて近い皮膜を形成し、その塗装法も従来の漆工技術ともよくなじみ、ここ数年の間に年産約2,000tonをあげる盛況を呈した。
※『ふってい(払底)』…品切れのこと。
伝統的な金継ぎで使用されるのは本漆
金継ぎは室町時代から始まったという説もあるほど、昔から行われてきた技術です。
もちろん昔の時代に合成うるしがあるはずもなく、古来からの伝統的な技法には漆の木から抽出される『本漆』を使用します。
また、金継ぎは本漆以外にも、小麦粉や金粉といった天然素材を使用して器を修復していきます。
簡易金継ぎは新うるしを使った金継ぎのこと
伝統的な金継ぎ技法では本漆を使用するとお伝えしてきました。
当たり前かもしれませんが、伝統技術ですから習得するのに時間がかかりますし、難易度も上がります。
乾くまでに時間が掛かるため、製作期間も2ヶ月以上とされています。
そんな伝統技術とは対照的なのが、簡易金継ぎです。
簡易金継ぎでは、上で説明した新うるしや、接着剤・エポキシパテなどの人工的な道具を使って器を修復します。
現代の便利な道具を使うことで、手軽に短い時間で金継ぎすることが可能です。
書籍などで紹介がキッカケで流行?
最近だと金継ぎのやり方の本が書店にたくさん並んでいます。
その中で有名になったのが、『はじめての金継ぎBOOK』という本です。
[itemlink post_id=”3887″]
この本には金継ぎの道具が入っていまして、本を読みながらスグに金継ぎができるようになっています。
(実際には少し道具が足りませんが…)

道具がセットになっている点もあってか、店頭でも大きく紹介されていました。
また、著者がナカムラクニオさんということで、知名度の大きさもあったと思います。
ただ、上の画像に表示されている通り、道具に入っているのは新うるしです。
なので、本に記載されている方法も新うるしを紹介しています。
簡易金継ぎは良くないこと?
このページをご覧になっている方の中には、すでに『簡易金継ぎ』や『新うるし』といった言葉で調べてみた方もいらっしゃると思います。
冒頭でもお伝えしたとおり、検索してみると、あまりよくないことが書かれているのではないでしょうか?
大きく2つのデメリットについて書かれていると思いますので、それぞれ紹介します。
理由1、伝統を守らない行為である
金継ぎは日本発祥の伝統工芸です。
日本以外でも『kintsugi』と呼ばれています。
そんな金継ぎですが、使われている本漆のシェアは9割が中国産となっており、日本のは1割ほどになります。
また、漆を木から採取するには漆掻き職人さんの力が必要なのですが、この職人さんたちも高齢化などが原因で年々減少しています。
「漆を守る、日本の伝統を守るという意味でも、合成うるしではなく本漆を使用するべき」というのが、簡易金継ぎが良くないと言われる理由の一つです。
理由2、道具が安全ではない
上で説明した通り、簡易金継ぎでは接着剤やエポキシパテといった道具を使用していきます。
こうした道具はホームセンターや東急ハンズなどで購入することができるのですが、市販されている物のほとんどが食器に使用できません。
「安全ではない道具を使用して修復した器を食器として使用しない方がいい」というのが、簡易金継ぎが良くないと言われる二つ目の理由です。
簡易金継ぎのやり方
まずは道具を揃えます。
必要最低限な道具は以下の通り。
- 割れた器をくっつける接着剤
- 欠けた部分やヒビの補正に使うエポキシパテ
- 紙ヤスリ(#400番と#1000番)
- 塗料(新うるし、合成うるし、絵の具など)
- 綿棒
- 彫刻刀(あると便利です)
- マスキングテープ(あると便利です)
- 竹串(あると便利です)
金継ぎ暮らしでは食器利用として認可された簡易金継ぎセットを販売しています。
以下は新うるしを使った簡易的な金継ぎのやり方の大まかな流れとなります。
割れている部分簡易金継ぎで接着します。
欠けた部分やヒビ部分を補修します。
補修した部分に金を入れていきます。
割れていない方は『STEP.1 接着』を飛ばして、『STEP.2 下地づくり』から始めてください。
STEP1 仮組みしてマスキングテープで仮止めして接着
まずは接着剤を使用せずに、割れた食器を仮組みしてマスキングテープで仮止めしましょう。
この際ですが、欠けなどによって多少の空白、隙間が出来ても大丈夫です。

仮止めをして完成イメージが出来たら、接着剤でくっつけます。
接着する時のポイントは以下の通りです。
- 接着剤は薄く塗る
- 接着した後にしばらく力を入れておさえる
付けた後はしばらく圧力を加えて接着(圧着)してください。
圧着は2分~5分程度行ってください。
上の写真のような小さい器であれば2分~3分程度でOKです。
大皿や器に厚みがある場合には、圧着する時間を長くしましょう。
付けた後に接着剤がハミ出した時は、綿棒をつかって拭き取ってください。

STEP2 下地作り、欠けた部分やヒビの補正
下地づくりは耐水エポキシパテを使った作業です。
- エポキシパテで形を作る
- 固まったエポキシパテを研ぐ
を行っていきます。
エポキシパテは内側と外側で成分が違う二重構造になっていて、混ぜ合わせることで凝固されます。
まずは5mm程度の輪切りにし、使いやすい大きさにカットしましょう。


適切な大きさにカットしたら混ぜ合わせます。
内側と外側を混ぜ合わせると凝固が始まるので、実際に手にとって使う直前に混ぜ合わせます。よく混ぜ合わせないと固まりづらい要因になるので、色にムラが出ないようにしっかり混ぜましょう。

混ぜ合わせたエポキシパテを使って欠けた部分の補正とヒビの補正を行います。
お皿の白い部分がエポキシパテで補正した部分です。できる限り元のお皿の形に近い形状になるように竹串などを使いながら補正していきます。

ヒビ(割れた箇所のつなぎ目)の部分にはエポキシパテを薄く伸ばしてヒビに沿って塗っていきます。

エポキシパテを少量ずつ、薄く伸ばしてお皿の裏表まんべんなく塗っていきましょう。

次に固まった余分なエポキシパテをヤスリや彫刻刀などで取り除きます。
使うヤスリは『#400番』です。
ヤスリの裏側に『400』と書かれている物を使ってください。
まずは削りたい部分に水をつけます。
水の量は少しで大丈夫なので、指で触れてつけられる程度で問題ありません。

- ヤスリを折り曲げたり小さく切ったりして、エポキシパテのサイズに合わせる
- 器に傷がつかないように、エポキシパテだけを削る
目をつぶって器を触ってみて、エポキシパテの場所がわからないくらい、器と一体化したらOKです。

ヒビ部分に塗ったエポキシパテもヤスリできれいに磨いていきます。
ヒビの部分では#1000番のヤスリを使います。

しっかり余分なエポキシパテを落とせたらステップ2の下地作りは完成です。

STEP.3 金を入れる
最後に表面に金(合成うるし、新うるし、塗料など)を入れて完成です。
本ページで紹介している新うるしの場合、
- 新うるし(金)
- 金粉(上記とセット)
- うすめ液
の3つを混ぜ合わせて使います。

混ぜ合わせた塗料をエポキシパテを塗った部分に塗っていきます。

塗り終わったら完成です。

金継ぎ暮らしでは、東京都内で「金継ぎ教室」を開催していますので興味のある方は下記ページを御覧ください。
遠方の方や自宅で体験してみたいという場合は、オンラインレッスンも受けられます。
- 新うるしは、実は漆ではない
- 金継ぎとして紹介されていても、実は簡易金継ぎの技法の場合もある
ということをお伝えしてきました。
ただ、ここまで詳しいことを知っている方はほとんどいないと思います。
金継ぎをよく知らない方からしたら、新うるしも
消費者庁でも以下のように分類しています。
天然の漆以外の塗料すなわちカシュー樹脂塗料、合成樹脂塗料等を塗ったものはその品名を示す用語を用いて適正に表示する。
植物性の樹液を主原料うるしではなく、うるしに似たような塗料のことを新うるしと呼んでいることが多いです。 “多い” と言っている理由は、そもそも『新うるし』という言葉自体が、商品名のことだからです。 元祖ふぐ印新うるしは、五十年以上も前に、江戸川工房が 新うるしの原料はカシュー樹脂塗料、合成樹脂塗料 、植物性の樹液を主原料とし、「漆っぽく見える」ように調合された「釣り具塗装のため」の合成塗料です。本物の天然の漆ではありません。くどいようですが「偽物」です。これから金継ぎを始める方は「金継ぎって全部同じなんじゃないの?」と思いますよね。 実は、金継ぎにはいろんなやり方がありまして、その中で使う道具が変わってきます。 そして、『簡易金継ぎ』というやり方の中で使われる道具が『新うるし』を使用するんです。 は植物性の樹液を主原料とし、「漆っぽく見える」ように調合された「釣り具塗装のため」の合成塗料です。本物の天然の漆ではありません。くどいようですが「偽物」です。
新うるしで金継ぎしようと考えている人は、安全な新うるしを使うようにしましょう。