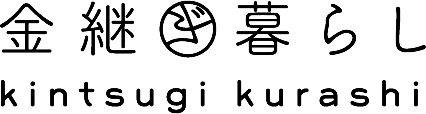佐賀県唐津市。
佐賀県の北西 玄界灘げんかいなだに面し、豊かな自然の中で唐津焼は作られています。
始まりは1580年頃。
お茶の世界では一楽二萩三唐津いちらくにはぎさんからつと呼ばれ、古くから茶人に愛される、歴史と伝統ある器です。
唐津焼の特徴

唐津焼は佐賀県唐津市を中心に生産されている焼き物です。
『土もの』と呼ばれる、シンプルながら力強さとあたたかさを持っています。
| 歴史 | 1580年ごろからはじまる |
|---|---|
| 作られている場所 | 佐賀県唐津市を中心に |
| 種類 | 陶器 |
| 窯元数 | 約70 |
| 土の特徴 | 力強く、焼き締まる。 |
日本独自の美意識である侘び寂びにもつながる器のシンプルさは、茶の湯の時代に茶人から特に愛されました。
京都の楽焼、山口の萩焼と合わせて、一楽二萩三唐津と言われています。
また京都・大阪をはじめとする西日本に広まっていくと、東の「瀬戸物」に対して西の「唐津物」と言われるほど焼き物の代名詞になり、
多くの人から親しまれました。
その後、磁器のブームにより一度衰退しますが、人間国宝・中里無庵(なかざと むあん)さんの功績により復活しました。
唐津焼の作られる工程
手で繰り返し土を練り、土の空気を抜いて硬さを均等にします。
轆轤を回転させながら、土を一つずつ器の形にしていきます。
器の高台の周りなどを削ります。
施文とも言われますが、鉄を使った絵具を筆入れしていきます。
石や灰、鉄などを混ぜたものを水に溶かした釉薬をうつわにかけます。
ひとつひとつ丁寧に窯に詰めていきます。
1300℃程にもなる高温で焼き上げられます。
唐津焼の魅力

唐津焼には「作り手八分、使い手二分」という理念があります。
この言葉は「作って完成ではなく使ってもらってこそ真の完成」という意味を持っています。
器は人々の生活の1部になってこそ、その美しさを発揮するという考え方です。
唐津焼の種類
唐津焼には柄、使う釉薬などによって様々な種類が存在します。
ここでは代表的な物を紹介します。
絵唐津(えがらつ)
草木や花、鳥などが描かれているのが特徴。
唐津焼は日本で初めて絵がつけられたと言われています。
斑唐津(まだらがらつ)
唐津焼が焼かれ始めた初期から現代まで作り続けられている。
白濁した釉薬を使い、表面に黒や青の斑点ができやすいことから名付けられました。
朝鮮唐津(ちょうせんがらつ)
二種類の釉薬を使い高温で焼くことで、自然に溶け合うコントラストを作ったもの。色のゆらめきの美しさが楽しめます。
唐津焼商人のそうじろうさんにインタビュー
ここからは佐賀県唐津市在住で唐津焼商人をしているそうじろうさんに当サイトが行なったインタビューを紹介します。
そうじろうさんは、唐津焼の魅力をもっと多くの人に知ってもらうために「唐津焼商人」をしている若き担い手
唐津焼と佐賀県グルメをコラボレーションしたイベントを開催するなど、積極的な活動をしています。
Q:商人を目指そうと思ったきっかけは?
私は、めちゃくちゃ地元大好き人間で何かしら地元に貢献して行きたいと思っていました
父が唐津焼の職人をしていて、普段から唐津焼には触れてました。
そんな中で、自分は商業高校に進学して今は佐賀大学の経済学部にいます。
今の自分ができることはなんだろうと考えた時に、今学んでいる知識と思いで父と仕事で協力しながら地元に貢献して行ければなんだかいい感じだなぁと思ったのがきっかけです。
Q:そうじろうさんの思う唐津焼の魅力は?
素朴な見た目の中に、それぞれの個性や迫力、派手さがあることと、長い間大切に使うと色味や摩耗などで2つとないものに変化していってどんどん愛着と自分だけのものになっていくところです!!
口当たりや手触りも土ものならではの温かさがあります!
Q:唐津の街の魅力や美味しいものは?
唐津は、11月2,3,4日にある「唐津くんち」というお祭りを中心に1年間があると言っても過言ではないくらいお祭りの街です。
名護屋城を始め、日本の歴史に欠かせないスポットや名産などがあり、歴史の流れを感じられると思います。
唐津は佐賀の北側の港町なので、イカを代表に新鮮な魚介類がおススメです!
Q:最近はどんな活動を行なっていますか?
最近は、窯元さんと会いたいという人を窯元さんへ繋ぐことをやっています。
夏には、大学の留学生を連れて、焼き物づくり体験と唐津市内観光を計画中です。他には、佐賀市内で「日本酒×唐津焼」、佐賀の「農作物×唐津焼」など唐津焼コラボでそれぞれの魅力を伝えるイベントを計画中です。
Q:唐津焼をどんな風に使ってもらいたいですか?
使い方は思いのままに素敵に使っていただきたいと思います。
私の楽しみ方は、長く使って色味や輝きなどが変わる「経年変化」を楽しんでいただきたいなぁと思っています。
それと、家の食器を全て唐津焼でそろえるではなく、有田焼などの磁器や海外の焼き物など、違う種類のものと組み合わせてみて欲しいです。唐津焼も組み合わせの相手も魅力がパワーアップすると思います。
そうじろうさんありがとうございました!!